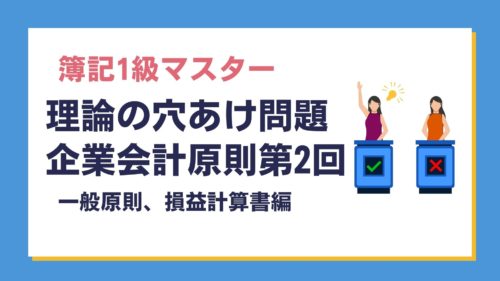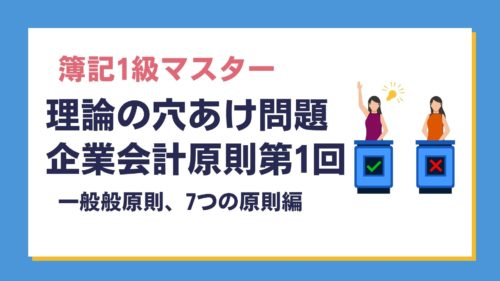二五 工程別総合原価計算
総合原価計算において、製造工程が二以上の連続する工程に分けられ、工程ごとにその工程製品の総合原価を計算する場合(この方法を「工程別総合原価計算」という。)には、一工程から次工程へ振り替えられた工程製品の総合原価を、前工程費又は原料費として( )に加算する。
この場合、工程間に振り替えられる工程製品の計算は、予定原価又は正常原価によることができる。
答はこちら
次工程の製造費用
二六 加工費工程別総合原価計算
原料がすべて最初の工程の始点で投入され、その後の工程では、単にこれを加工するにすぎない場合には、各工程別に一期間の加工費を集計し、それに原料費を加算することにより、完成品総合原価を計算する。この方法を加工費工程別総合原価計算(加工費法)という。
二七 仕損および減損の処理
総合原価計算においては、仕損の費用は、原則として、特別に仕損費の費目を設けることをしないで、これをその期の( )と( )とに負担させる。
加工中に蒸発、粉散、ガス化、煙化等によって生ずる原料の減損の処理は、仕損に準ずる。
答はこちら
完成品、期末仕掛品
二八 副産物等の処理と評価
総合原価計算において、副産物が生ずる場合には、その価額を算定して、これを主産物の総合原価から控除する。副産物とは、主産物の製造過程から必然に派生する物品をいう。
副産物の価額は、次のような方法によって算定した額とする。
(一) 副産物で、そのまま外部に売却できるものは、見積売却価額から販売費および一般管理費又は販売費、一般管理費および( )の見積額を控除した額。
答はこちら
通常の利益
(二) 副産物で、加工の上売却できるものは、加工製品の見積売却価額から加工費、販売費および一般管理費又は加工費、販売費、一般管理費および通常の利益の見積額を控除した額。
(三) 副産物で、そのまま自家消費されるものは、これによって節約されるべき物品の見積購入価額
(四) 副産物で、加工の上自家消費されるものは、これによって節約されるべき物品の見積購入価額から加工費の見積額を控除した額
軽微な副産物は、前項の手続によらないで、これを売却して得た収入を、原価計算外の収益とすることができる。
作業くず、仕損品等の処理および評価は、副産物に準ずる。
二九 連産品の計算
連産品とは、同一工程において同一原料から生産される異種の製品であって、相互に主副を明確に区別できないものをいう。
連産品の価額は、連産品の正常市価等を基準として定めた等価係数に基づき、一期間の総合原価を連産品にあん分して計算する。
この場合、連産品で、加工の上売却できるものは、加工製品の見積売却価額から加工費の見積額を控除した額をもって、その正常市価とみなし、等価係数算定の基礎とする。
ただし、必要ある場合には、連産品の一種又は数種の価額を副産物に準じて計算し、これを一期間の総合原価から控除した額をもって、他の連産品の価額とすることができる。
三〇 総合原価計算における直接原価計算
総合原価計算において、必要ある場合には、一期間における製造費用のうち、変動直接費および変動間接費のみを部門に集計して部門費を計算し、これに期首仕掛品を加えて完成品と期末仕掛品とにあん分して製品の直接原価を計算し、固定費を製品に集計しないことができる。
この場合、会計年度末においては、当該会計期間に発生した固定費額は、これ( )と( )とに配賦する。
答はこちら
を期末の仕掛品および製品、当年度の売上品
三一 個別原価計算
個別原価計算は、種類を異にする製品を個別的に生産する生産形態に適用する。
個別原価計算にあっては、特定製造指図書について個別的に直接費および間接費を集計し、製品原価は、これを当該指図書に含まれる製品の生産完了時に算定する。
経営の目的とする製品の生産に際してのみでなく、自家用の建物、機械、工具等の製作又は修繕、試験研究、試作、仕損品の補修、仕損による代品の製作等に際しても、これを特定指図書を発行して行なう場合は、個別原価計算の方法によってその原価を算定する。
三二 直接費の賦課
個別原価計算における直接費は、発生のつど又は定期に整理分類して、これを当該指図書に賦課する。
(一) 直接材料費は、当該指図書に関する実際消費量に、その消費価格を乗じて計算する。消費価格の計算は、第二節一一の(三)に定めるところによる。
自家生産材料の消費価格は、実際原価又は予定価格等をもって計算する。
(二) 直接労務費は、当該指図書に関する実際の作業時間又は作業量に、その賃率を乗じて計算する。賃率の計算は、第二節一二の(一)に定めるところによる。
(三) 直接経費は、原則として当該指図書に関する( )をもって計算する。
答はこちら
実際発生額
三三 間接費の配賦
(一) 個別原価計算における間接費は、原則として部門間接費として各指図書に配賦する。
(二) 間接費は、原則として( )をもって各指図書に配賦する。
答はこちら
予定配賦率
(三) 部門間接費の予定配賦率は、一定期間における各部門の間接費予定額又は各部門の固定間接費予定額および変動間接費予定額を、それぞれ同期間における当該部門の予定配賦基準をもって除して算定する。
(四) 一定期間における各部門の間接費予定額又は各部門の固定間接費予定額および変動間接費予定額は、次のように計算する。
1 まず、間接費を固定費および変動費に分類して、過去におけるそれぞれの原価要素の実績をは握する。この場合、間接費を固定費と変動費とに分類するためには、間接費要素に関する各費目を調査し、費目によって固定費又は変動費のいずれかに分類する。準固定費又は準変動費は、実際値の変化の調査に基づき、これを固定費又は変動費とみなして、そのいずれかに帰属させるか、もしくはその固定費部分および変動費率を測定し、これを固定費と変動費とに分解する。
2 次に、将来における物価の変動予想を考慮して、これに修正を加える。
3 さらに固定費は、設備計画その他固定費に影響する計画の変更等を考慮し、変動費は、製造条件の変更等変動費に影響する条件の変化を考慮して、これを修正する。
4 変動費は、予定操業度に応ずるように、これを算定する。
(五) 予定配賦率の計算の基礎となる予定操業度は、原則として、一年又は一会計期間において予期される操業度であり、それは、技術的に達成可能な最大操業度ではなく、この期間における生産ならびに販売事情を考慮して定めた操業度である。
操業度は、原則として直接作業時間、機械運転時間、生産数量等間接費の発生と関連ある適当な( )によって、これを表示する。
操業度は、原則としてこれを各部門に区分して測定表示する。
答はこちら
物量基準
(六) 部門間接費の各指図書への配賦額は、各製造部門又はこれを細分した各小工程又は各作業単位別に、次のいずれかによって計算する。
1 間接費予定配賦率に、各指図書に関する実際の配賦基準を乗じて計算する。
2 固定間接費予定配賦率および変動間接費予定配賦率に、それぞれ各指図書に関する実際の配賦基準を乗じて計算する。
(七) 一部の補助部門費を製造部門に配賦しないで、直接に指図書に配賦する場合には、そのおのおのにつき適当な基準を定めてこれを配賦する。
この簿記1級の理論問題は、製造業の原価計算方法に関するものです。特に、工程別総合原価計算、加工費工程別総合原価計算、仕損および減損の処理、副産物等の処理と評価、連産品の計算、総合原価計算における直接原価計算、個別原価計算、直接費の賦課、間接費の配賦といったテーマに焦点を当てています。以下にそれぞれの要点を簡潔にまとめ、解説を加えます。
工程別総合原価計算
- 要点: 製造工程が複数に分かれている場合、各工程で発生した原価を次工程に原料費として振り替えて計算します。
- 解説: この方法は、連続生産過程を持つ製品に適しており、各工程の効率分析やコスト管理に役立ちます。
加工費工程別総合原価計算(加工費法)
- 要点: 最初の工程で全原料を投入し、以降の工程では加工のみを行う場合、各工程の加工費に原料費を加えて完成品の原価を計算します。
- 解説: 原料のコストが主要なコスト要素であり、加工工程が複数ある場合に適用されます。
仕損および減損の処理
- 要点: 仕損や原料の自然減少分は通常、その期の原価に含めて負担させます。
- 解説: これにより、実際に発生したコストを正確に反映し、原価計算の正確性を高めます。
副産物等の処理と評価
- 要点: 副産物の価額を主産物の総合原価から控除し、正確な主産物の原価を計算します。
- 解説: 副産物の適正な評価により、主産物の原価計算の精度を向上させることができます。
連産品の計算
- 要点: 同一工程で生産される異なる製品(連産品)の原価は、正常市価を基に等価係数を用いて分配計算します。
- 解説: 連産品はそれぞれ市場価値が異なるため、等価係数を用いることで公平な原価分配を図ります。
総合原価計算における直接原価計算
- 要点: 必要に応じて、変動費のみを製品原価に計上し、固定費は期末で一括して計算する方法があります。
- 解説: この方法は、固定費と変動費の区分が明確で、変動費の管理に焦点を当てたい場合に有効です。
個別原価計算
- 要点: 種類が異なる製品を個別に生産する場合、直接費と間接費を製品ごとに集計して原価を計算します。
- 解説: 特定の製品やプロジェクト
のコスト管理に適しており、正確なコスト評価が可能になります。
直接費の賦課
- 要点: 直接材料費、直接労務費、直接経費を製品や指図書ごとに計算し、賦課します。
- 解説: 直接費は製品に直接関連する費用であり、正確な原価計算の基礎となります。
間接費の配賦
- 要点: 間接費は原則として、製造部門や指図書に基づいて配賦されます。
- 解説: 間接費の適切な配賦により、各製品の原価を正確に反映させることができます。
これらの原価計算方法は、製造業におけるコスト管理や価格設定の基礎となり、効率的な運営と競争力の向上に寄与します。