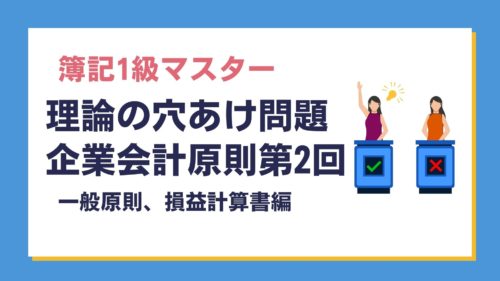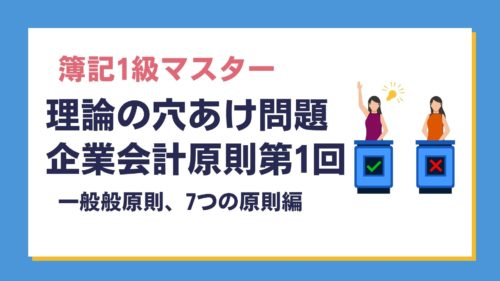四三 標準原価の指示
標準原価は、一定の文書に表示されて原価発生について責任をもつ各部署に指示されるとともに、この種の文書は、標準原価会計機構における補助記録となる。
標準原価を指示する文書の種類、記載事項および様式は、経営の特質によって適当に定めるべきであるが、たとえば次のようである。
(一) 標準製品原価表
標準製品原価表とは、( )に指定された製品の一定単位当たりの標準原価を構成する各種直接材料費の標準、作業種類別の直接労務費の標準および部門別製造間接費配賦額の標準を数量的および金額的に表示指定する文書をいい、必要に応じ材料明細表、標準作業表等を付属させる。
答はこちら
製造指図書
(二) 材料明細表
材料明細表とは、製品の一定単位の生産に必要な直接材料の種類、品質、その標準消費数量等を表示指定する文書をいう。
(三) 標準作業表
標準作業表とは、製品の一定単位の生産に必要な区分作業の種類、作業部門、使用機械工具、作業の内容、労働等級、各区分作業の標準時間等を表示指定する文章をいう。
(四) 製造間接費予算表
製造間接費予算表は、製造間接費予算を費目別に表示指定した費目別予算表と、これをさらに部門別に表示指定した部門別予算表とに分けられ、それぞれ予算期間の総額および各月別予算額を記載する。部門別予算表において、必要ある場合には、費目を変動費と固定費又は管理可能費と管理不能費とに区分表示する。
第四章 原価差異の算定および分析
四四 原価差異の算定および分析
原価差異とは実際原価計算制度において、原価の一部を予定価格等をもって計算した場合における原価と実際発生額との間に生ずる差額、ならびに標準原価計算制度において、標準原価と実際発生額との間に生ずる差額(これを「( )」となづけることがある。)をいう。
答はこちら
標準差異
原価差異が生ずる場合には、その大きさを算定記録し、これを分析する。その目的は、原価差異を財務会計上適正に処理して製品原価および損益を確定するとともに、その分析結果を各階層の( )に提供することによって、原価の管理に資することにある。
答はこちら
経営管理者
四五 実際原価計算制度における原価差異
実際原価計算制度において生ずる主要な原価差異は、おおむね次のように分けて算定する。
(一) 材料副費配賦差異
材料副費配賦差異とは、材料副費の一部又は全部を( )をもって材料の購入原価に算入することによって生ずる原価差異をいい、一期間におけるその材料副費の配賦額と実際額との差額として算定する。
答はこちら
予定配賦率
(二) 材料受入価格差異
材料受入価格差異とは、材料の受入価格を予定価格等をもって計算することによって生ずる原価差異をいい、一期間におけるその材料の受入金額と( )との差額として算定する。
答はこちら
実際受入金額
(三) 材料消費価格差異
材料消費価格差異とは、材料の消費価格を予定価格等をもって計算することによって生ずる原価差異をいい、一期間におけるその材料費額と( )との差額として計算する。
答はこちら
実際発生額
(四) 賃率差異
賃率差異とは、労務費を( )をもって計算することによって生ずる原価差異をいい、一期間におけるその労務費額と実際発生額との差額として算定する。
答はこちら
予定賃率
(五) 製造間接費配賦差異
製造間接費配賦差異とは、製造間接費を予定配賦率をもって製品に配賦することによって生ずる原価差異をいい、一期間における( )と実際額との差額として算定する。
答はこちら
その製造間接費の配賦額
(六) 加工費配賦差異
加工費配賦差異とは、部門加工費を予定配賦率をもって製品に配賦することによって生ずる原価差異をいい、一期間におけるその加工費の配賦額と( )との差額として算定する。
答はこちら
実際額
(七) 補助部門費配賦差異
補助部門費配賦差異とは、補助部門費を予定配賦率をもって製造部門に配賦することによって生ずる原価差異をいい、一期間におけるその補助部門費の配賦額と実際額との差額として算定する。
(八) 振替差異
振替差異とは、工程間に振り替えられる工程製品の価額を予定原価又は正常原価をもって計算することによって生ずる原価差異をいい、( )と実際額との差額として算定する。
答はこちら
一期間におけるその工程製品の振替価額
四六 標準原価計算制度における原価差額
標準原価計算制度において生ずる主要な原価差異は、材料受入価額、直接材料費、直接労務費および製造間接費のおのおのにつき、おおむね次のように算定分析する。
(一) 材料受入価格差異
材料受入価格差異とは、材料の受入価格を標準価格をもって計算することによって生ずる原価差異をいい、標準受入価格と実際受入価格との差異に、( )を乗じて算定する。
答はこちら
実際受入数量
(二) 直接材料費差異
直接材料費差異とは、標準原価による直接材料費と直接材料費の実際発生額との差額をいい、これを材料種類別に価格差異と数量差異とに分析する。
1 価格差異とは、材料の標準消費価格と実際消費価格との差異に基づく直接材料費差異をいい、直接材料の標準消費価格と( )との差異に、実際消費数量を乗じて算定する。
答はこちら
実際消費価格
2 数量差異とは、材料の標準消費数量と実際消費数量との差異に基づく直接材料費差異をいい、直接材料の標準消費数量と実際消費数量との差異に、( )を乗じて算定する。
答はこちら
標準消費価格
(三) 直接労務費差異
直接労務費差異とは、標準原価による直接労務費と直接労務費の実際発生額との差額をいい、これを部門別又は作業種類別に賃率差異と作業時間差異とに分析する。
1 賃率差異とは、標準賃率と実際賃率との差異に基づく直接労務費差異をいい、標準賃率と実際賃率との差異に、( )を乗じて算定する。
答はこちら
実際作業時間
2 作業時間差異とは、標準作業時間と実際作業時間との差額に基づく直接労務費差異をいい、標準作業時間と実際作業時間との差異に、( )を乗じて算定する。
答はこちら
標準賃率
(四) 製造間接費差異
製造間接費差異とは、製造間接費の標準額と実際発生額との差額をいい、原則として一定期間における部門間接費差異として算定して、これを( )、( )等に適当に分析する。
答はこちら
能率差異、操業度差異
第五章 原価差異の会計処理
四七 原価差異の会計処理
(一) 実際原価計算制度における原価差異の処理は、次の方法による。
1 原価差異は、材料受入価格差異を除き、原則として当年度の( )に賦課する。
答はこちら
売上原価
2 材料受入価格差異は、当年度の材料の( )と期末在高に配賦する。この場合、材料の期末在高については、材料の適当な種類群別に配賦する。
答はこちら
払出高
3 予定価格等が不適当なため、比較的多額の原価差異が生ずる場合、直接材料費、直接労務費、直接経費および製造間接費に関する原価差異の処理は、次の方法による。
(1) 個別原価計算の場合
次の方法のいずれかによる。
イ 当年度の売上原価と期末におけるたな卸資産に指図書別に配賦する。
ロ 当年度の売上原価と期末におけるたな卸資産に科目別に配賦する。
(2) 総合原価計算の場合
当年度の売上原価と期末におけるたな卸資産に科目別に配賦する。
(二) 標準原価計算制度における原価差異の処理は、次の方法による。
1 数量差異、作業時間差異、能率差異等であって異常な状態に基づくと認められるものは、これを( )として処理する。
答はこちら
非原価項目
2 前記1の場合を除き、原価差異はすべて実際原価計算制度における処理の方法に準じて処理する。
この簿記1級の理論問題の要点は、標準原価の指示、原価差異の算定と分析、および原価差異の会計処理に関するものです。以下にそれぞれのセクションの要点と解説をまとめます。
標準原価の指示
標準原価は、製品やサービスの製造において事前に定められた原価の基準です。これには、直接材料費、直接労務費、および製造間接費が含まれます。標準原価を指示する主要な文書には以下があります:
- 標準製品原価表:製品の単位ごとに直接材料費、直接労務費、および部門別製造間接費の標準を示します。
- 材料明細表:製品製造に必要な直接材料の種類、品質、標準消費数量を示します。
- 標準作業表:製造プロセスで必要な作業の種類、部門、使用機械、労働等級、および標準時間を示します。
- 製造間接費予算表:製造間接費を費目別、部門別に予算化し、固定費と変動費、管理可能費と管理不能費に分けて表示します。
原価差異の算定および分析
原価差異は、計画された(標準)原価と実際に発生した原価との差です。この差異を分析することで、原価管理の効率化や製品の原価削減に役立てることができます。主な原価差異には以下のものがあります:
- 材料副費配賦差異:材料副費の配賦によって生じる差異。
- 材料受入価格差異:材料の受入価格の予定値と実際値の差異。
- 材料消費価格差異:材料消費時の価格差異。
- 賃率差異:労務費の計算基準と実際の差異。
- 製造間接費配賦差異:製造間接費の配賦による差異。
- 加工費配賦差異、補助部門費配賦差異:それぞれ加工費と補助部門費の配賦による差異。
- 振替差異:工程間での製品価額の振替えによる差異。
原価差異の会計処理
原価差異の会計処理には、実際原価計算制度と標準原価計算制度の処理方法があります。実際原価計算制度では、原価差異を当年度の製品原価や損益計算に反映させます。標準原価計算制度では、異常な状況に基づく差異は異常損失として処理し、それ以外の原価差異は実際原価計算制度に準じた方法で処理します。
これらの概念と手法を理解し、適切に適用することで、経営者や財務担当者は原価をより効率的に管理し、企業の利益向上に貢献することができます。