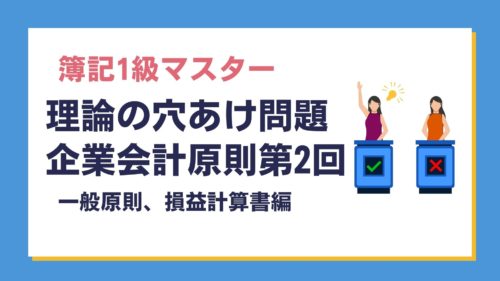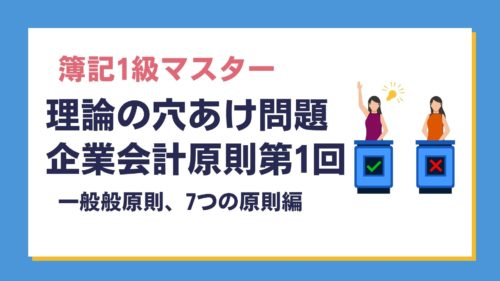一一 材料費計算
(一) 直接材料費、補助材料費等であって、出入記録を行なう材料に関する原価は、各種の材料につき原価計算期間における( )に、その( )を乗じて計算する。
答はこちら
実際の消費量、消費価格
(二) 材料の実際の消費量は、原則として( )によって計算する。ただし、材料であって、その消費量を継続記録法によって計算することが困難なもの又はその必要のないものについては、たな卸計算法を適用することができる。
答はこちら
継続記録法
(三) 材料の消費価格は、原則として( )をもって計算する。
答はこちら
購入原価
同種材料の購入原価が異なる場合、その消費価格の計算は、次のような方法による。
1 先入先出法
2 移動平均法
3 総平均法
4 後入先出法
5 個別法
材料の消費価格は、必要ある場合には、予定価格等をもって計算することができる。
(四) 材料の購入原価は、原則として実際の購入原価とし、次のいずれかの金額によって計算する。
1 購入代価に買入手数料、引取運賃、荷役費、保険料、関税等材料買入に要した引取費用を加算した金額
2 購入代価に引取費用ならびに購入事務、検収、整理、選別、手入、保管等に要した費用(引取費用と合わせて以下これを「材料副費」という。)を加算した金額。ただし、必要ある場合には、引取費用以外の材料副費の一部を購入代価に加算しないことができる。
購入代価に加算する材料副費の一部又は全部は、これを予定配賦率によって計算することができる。予定配賦率は、一定期間の材料副費の予定総額を、その期間における材料の予定購入代価又は予定購入数量の総額をもって除して算定する。ただし、購入事務費、検収費、整理費、選別費、手入費、保管費等については、それぞれに適当な予定配賦率を設定することができる。
材料副費の一部を材料の購入原価に算入しない場合には、これを間接経費に属する項目とし又は材料費に配賦する。
購入した材料に対して値引又は割戻等を受けたときは、これを材料の購入原価から控除する。ただし、値引又は割戻等が材料消費後に判明した場合には、これを同種材料の購入原価から控除し、値引又は割戻等を受けた材料が判明しない場合には、これを当期の材料副費等から控除し、又はその他適当な方法によって処理することができる。
材料の購入原価は、必要ある場合には、( )等をもって計算することができる。
答はこちら
予定価格
他工場からの振替製品の受入価格は、必要ある場合には、正常市価によることができる。
(五) 間接材料費であって、工場消耗品、消耗工具器具備品等、継続記録法又はたな卸計算法による出入記録を行わないものの原価は、原則として当該原価計算期間における買入額をもって計算する。
一二 労務費計算
(一) 直接賃金等であって、作業時間又は作業量の測定を行なう労務費は、実際の作業時間又は作業量に( )を乗じて計算する。賃率は、実際の個別賃率又は、職場もしくは作業区分ごとの平均賃率による。平均賃率は、必要ある場合には、予定平均賃率をもって計算することができる。
答はこちら
賃率
直接賃金等は、必要ある場合には、当該原価計算期間の負担に属する要支払額をもって計算することができる。
(二) 間接労務費であって、間接工賃金、給料、賞与手当等は、原則として当該原価計算期間の負担に属する要支払額をもって計算する。
一三 経費計算
(一) 経費は、原則として当該原価計算期間の( )をもって計算する。ただし、必要ある場合には、予定価格又は予定額をもって計算することができる。
答はこちら
実際の発生額
(二) 減価償却費、不動産賃借料等であって、数ヶ月分を一時に総括的に計算し又は支払う経費については、これを月割り計算する。
(三) 電力料、ガス代、水道料等であって、消費量を計量できる経費については、その実際消費量に基づいて計算する。
一四 費用別計算における予定価格等の適用
費目別計算において一定期間における原価要素の発生を測定するに当たり、予定価格等を適用する場合には、これをその適用される期間における実際価格にできる限り近似させ、価格差異をなるべく僅少にするように定める。
第三節 原価の部門別計算
一五 原価の部門別計算
原価の部門別計算とは、費目別計算においては握された原価要素を、原価部門別に分類集計する手続をいい、原価計算における( )の計算段階である。
答はこちら
第二次
一六 原価部門の設定
原価部門とは、原価の発生を機能別、責任区分別に管理するとともに、製品原価の計算を正確にするために、原価要素を分類集計する計算組織上の区分をいい、これを諸製造部門と諸補助部門とに分ける。製造および補助の諸部門は、次の基準により、かつ、経営の特質に応じて適当にこれを区分設定する。
(一) 製造部門
製造部門とは、直接製造作業の行なわれる部門をいい、製品の種類別、製品生成の段階、製造活動の種類別等にしたがって、これを各種の部門又は工程に分ける。たとえば機械製作工場における鋳造、鍛造、機械加工、組立等の各部門はその例である。
副産物の加工、包装品の製造等を行なういわゆる副経営は、これを製造部門とする。
製造に関する諸部門は、必要ある場合には、さらに機械設備の種類、作業区分等にしたがって、これを各小工程又は各作業単位に細分する。
(二) 補助部門
補助部門とは、製造部門に対して補助的関係にある部門をいい、これを補助経営部門と工場管理部門とに分け、さらに機能の種類別等にしたがって、これを各種の部門に分ける。
補助経営部門とは、その事業の目的とする製品の生産に直接関与しないで、自己の製品又は用役を製造部門に提供する諸部門をいい、たとえば( )、( )、( )、工具製作部、検査部等がそれである。
答はこちら
動力部、修繕部、運搬部、
工具製作、修繕、動力等の補助経営部門が相当の規模となった場合には、これを独立の経営単位とし、計算上製造部門として取り扱う。
工場管理部門とは、管理的機能を行なう諸部門をいい、たとえば材料部、労務部、企画部、試験研究部、工場事務部等がそれである。
一七 部門個別費と部門共通費
原価要素は、これを原価部門に分類集計するに当たり、当該部門において発生したことが直接的に認識されるかどうかによって、( )と( )に分類する。
答はこちら
部門個別費、部門共通費
部門個別費は、原価部門における発生額を直接に当該部門に賦課し、部門共通費は、原価要素別に又はその性質に基づいて分類された原価要素群別にもしくは一括して、適当な配賦基準によって関係各部門に配賦する。部門共通費であって工場全般に関して発生し、適当な配賦基準の得がたいものは、これを一般費とし、補助部門費として処理することができる。
一八 部門別計算の手続
(一) 原価要素の全部又は一部は、まずこれを各製造部門および補助部門に賦課又は配賦する。この場合、部門に集計する原価要素の範囲は、製品原価の正確な計算および原価管理の必要によってこれを定める。たとえば、個別原価計算においては、製造間接費のほか、直接労務費をも製造部門に集計することがあり、総合原価計算においては、すべての製造原価要素又は加工費を製造部門に集計することがある。
各部門に集計された原価要素は、必要ある場合には、これを( )と( )又は管理可能費と管理不能費とに区分する。
答はこちら
変動費、固定費
(二) 次いで補助部門費は、( )、( )、相互配賦等にしたがい、適当な配賦基準によって、これを各製造部門に配賦し、製造部門費を計算する。
答はこちら
直接配賦法、階梯式配賦法
一部の補助部門費は、必要ある場合には、これを製造部門に配賦しないで直接に製品に配賦することができる。
(三) 製造部門に集計された原価要素は、必要に応じさらにこれをその部門における小工程又は作業単位に集計する。この場合、小工程又は作業単位には、その小工程等において管理可能の原価要素又は直接労務費のみを集計し、そうでないものは共通費および他部門配賦費とする。
この理論問題の要点をまとめると、簿記1級の試験における材料費、労務費、経費計算に関する基本的な原則と、原価計算における部門別計算の概念について述べられています。以下にそれぞれの要点を解説します。
材料費計算
- 直接材料費の計算: 直接材料費は、製品製造に直接使用される材料のコストです。これは原価計算期間における実際の消費量に基づいて計算されます。通常は実際の消費量を記録し、計算に利用しますが、難しい場合や不要な場合は、たな卸し計算法(在庫の物理的なカウントに基づく方法)を使用することが許されます。
- 材料の消費価格: 消費価格は通常、実際の購入価格を基に計算されますが、価格の変動がある場合は先入先出法(FIFO)、移動平均法、総平均法、後入先出法(LIFO)、個別法などの方法を用いて消費価格を決定します。
- 材料費に含まれる費用: 材料の購入原価には、購入価格の他に運送費、保険料、関税などの追加費用が含まれることがあります。また、これらの副費用の一部を購入価格に加算することができ、計算には予定配賦率が用いられることがあります。
労務費計算
- 直接労務費の計算: 直接労務費は、製品製造に直接携わる労働者の賃金で、実際の作業時間または作業量に基づいて計算されます。賃率は個別の実際の賃率や作業区分ごとの平均賃率を使用して決定されます。
- 間接労務費: 間接労務費は製造直接費には含まれないが、製造過程で発生する労務費で、原則として原価計算期間の負担額に基づいて計算されます。
経費計算
- 経費の計算: 経費は、一般的に原価計算期間の実際の費用に基づいて計算されますが、予定価格や予定額を使用することも可能です。
- 特定の経費の計算方法: 一括して支払われる経費(例:減価償却費)は月割り計算がなされ、消費量を計量できる経費(例:電力料金)は実際の消費量に基づいて計算されます。
原価の部門別計算
- 原価部門の設定: 原価を効果的に管理し、製品原価を正確に計算するために、原価を発生させる部門ごとに分類します。これには製造部門と補助部門が含まれます。
- 部門費の計算: 部門別の原価要素は部門個別費と部門共通費に分類され、適切な配賦基準によって各部門に配分されます。
この解説は、簿記1級の理論問題の要点を簡潔にまとめたものであり、各項目の詳細な理解にはさらなる学習が必要です。