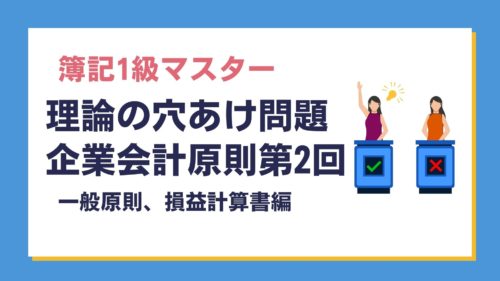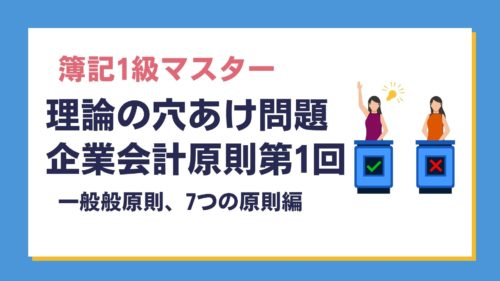[注6] 実現主義の適用について
委託販売、試用販売、予約販売、割賦販売等特殊な販売契約による売上収益の実現の基準は、次によるものとする。
委託販売
委託販売については、( )した日をもって売上収益の実現の日とする。従って、決算手続中に仕切精算書(売上計算書)が到達すること等により決算日までに販売された事実が明らかとなったものについては、これを当期の売上収益に計上しなければならない。ただし、仕切精算書が販売のつど送付されている場合には、当該仕切精算書が到達した日をもって売上収益の実現の日とみなすことができる。
答はこちら
受託者が委託品を販売
試用販売
試用販売については、( )することによって売上が実現するのであるから、それまでは、当期の売上高に計上してはならない。
答はこちら
得意先が買取りの意思を表示
予約販売
予約販売については、予約金受取額のうち、決算日までに( )した分だけを当期の売上高に計上し、残額は貸借対照表の負債の部に記載して次期以後に繰延べなければならない。
答はこちら
商品の引渡し又は役務の給付が完了
割賦販売
割賦販売については、商品等を引渡した日をもって売上収益の実現の日とする。 しかし、割賦販売は通常の販売と異なり、その代金回収の期間が長期にわたり、かつ、分割払であることから代金回収上の危険が高いので、貸倒引当金及び代金回収費、アフター・サービス費等の引当金の計上について特別の配慮を要するが、その算定に当たっては、( )とを伴う場合が多い。従って、収益の認識を慎重に行うため、販売基準に代えて、割賦金の回収期限の到来の日又は入金の日をもって売上収益実現の日とすることも認められる。
答はこちら
不確実性と煩雑さ
[注7] 工事収益について
長期の請負工事に関する収益の計上については、工事進行基準又は( )のいずれかを選択適用することができる。
答はこちら
工事完成基準
工事進行基準
決算期末に( )を見積り、適正な工事収益率によって工事収益の一部を当期の損益計算に計上する。
答はこちら
工事進行程度
工事完成基準
工事が完成し、その( )が完了した日に工事収益を計上する。
答はこちら
引渡し
[注8] 製品等の製造原価について
製品等の製造原価は、適正な原価計算基準に従って算定しなければならない。
[注9] 原価差額の処理について
原価差額を売上原価に賦課した場合には、損益計算書に売上原価の内訳科目として次の形式で原価差額を記載する。
売上原価
1 期首製品たな卸高×××
2 当期製品製造原価×××
合 計×××
3 期末製品たな卸高×××
標準(予定)売上原価×××
4 原価差額××××××
原価差額をたな卸資産の科目別に配賦した場合には、これを貸借対照表上のたな卸資産の科目別に各資産の価額に含めて記載する。
[注10] たな卸資産の評価損について
商品、製品、原材料等のたな卸資産に低価基準を適用する場合に生ずる評価損は、原則として、売上原価の内訳科目又は( )として表示しなければならない。
答はこちら
営業外費用
時価が取得原価より著しく下落した場合の評価損は、原則として、営業外費用又は特別損失として表示しなければならない。
品質低下、陳腐化等の原因によって生ずる評価損については、それが原価性を有しないものと認められる場合には、これを営業外費用又は特別損失として表示し、これらの評価損が原価性を有するものと認められる場合には、製造原価、売上原価の内訳科目又は( )として表示しなければならない。
答はこちら
販売費
[注11] 内部利益とその除去の方法について
内部利益とは、原則として、本店、支店、事業部等の企業内部における独立した会計単位相互間の内部取引から生ずる未実現の利益をいう。従って、( )における原材料、半製品等の振替から生ずる振替損益は内部利益ではない。
答はこちら
会計単位内部
内部利益の除去は、本支店等の合併損益計算書において売上高から内部売上高を控除し、仕入高(又は売上原価)から内部仕入高(又は内部売上原価)を控除するとともに、期末たな卸高から内部利益の額を控除する方法による。これらの控除に際しては、( )によることも差支えない。
答はこちら
合理的な見積概算額
[注12] 特別損益項目について
特別損益に属する項目としては、次のようなものがある。
(1) 臨時損益
イ 固定資産売却損益
ロ 転売以外の目的で取得した有価証券の売却損益
ハ 災害による損失
(2) 前期損益修正
イ 過年度における引当金の過不足修正額
ロ 過年度における減価償却の過不足修正額
ハ 過年度におけるたな卸資産評価の訂正額
なお、特別損益に属する項目であっても、金額の僅少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益計算に含めることができる。
[注13] 法人税等の追徴税額等について
法人税等の更正決定等による追徴税額及び還付税額は、税引前当期純利益に加減して表示する。この場合、当期の負担に属する法人税額等とは区別することを原則とするが、重要性の乏しい場合には、当期の負担に属するものに含めて表示することができる。
[注14] 削除
[注15] 将来の期間に影響する特定の費用について
「将来の期間に影響する特定の費用」とは、すでに( )が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう。
答はこちら
対価の支払が完了し又は支払義務
これらの費用は、その効果が及ぶ数期間に合理的に配分するため、経過的に貸借対照表上繰延資産として計上することができる。
なお、天災等により固定資産又は企業の営業活動に必須の手段たる資産の上に生じた損失が、その期の純利益又は当期未処分利益から当期の処分予定額を控除した金額をもって負担しえない程度に巨額であって特に法令をもって認められた場合には、これを経過的に貸借対照表の資産の部に記載して繰延経理することができる。
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
受取手形、売掛金、前払金、支払手形、買掛金、前受金等の当該企業の主目的たる営業取引により発生した債権及び債務は、流動資産又は流動負債に属するものとする。ただし、これらの債権のうち、破産債権、更正債権及びこれに準ずる債権で( )に回収されないことが明らかなものは、固定資産たる投資その他の資産に属するものとする。
答はこちら
一年以内
貸付金、借入金、差入保証金、受入保証金、当該企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が一年をこえて到来するものは、投資その他の資産又は固定負債に属するものとする。
現金預金は、原則として、流動資産に属するが、預金については、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に期限が到来するものは、流動資産に属するものとし、期限が一年をこえて到来するものは、( )に属するものとする。
答はこちら
投資その他の資産
所有有価証券のうち、証券市場において流通するもので、短期的資金運用のために一時的に所有するものは、流動資産に属するものとし、証券市場において流通しないもの若しくは他の企業を支配する等の目的で長期的に所有するものは、投資その他の資産に属するものとする。
前払費用については、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に費用となるものは、流動資産に属するものとし、一年をこえる期間を経て費用となるものは、( )に属するものとする。未収収益は流動資産に属するものとし、未払費用及び前受収益は、流動負債に属するものとする。
答はこちら
投資その他の資産
商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等のたな卸資産は、流動資産に属するものとし、企業がその営業目的を達成するために所有し、かつ、その( )は、固定資産に属するものとする。
答はこちら
加工若しくは売却を予定しない財貨
なお、固定資産のうち残存耐用年数が一年以下となったものも流動資産とせず固定資産に含ませ、たな卸資産のうち恒常在庫品として保有するもの若しくは余剰品として長期間にわたって所有するものも固定資産とせず流動資産に含ませるものとする。
[注17] 貸倒引当金又は減価償却累計額の控除形式について
貸倒引当金又は減価償却累計額は、その債権又は有形固定資産が属する科目ごとに( )する形式で表示することを原則とするが、次の方法によることも妨げない。
答はこちら
控除
二以上の科目について、貸倒引当金又は減価償却累計額を一括して記載する方法
債権又は有形固定資産について、貸倒引当金又は減価償却累計額を控除した残額のみを記載し、当該貸倒引当金又は減価償却累計額を注記する方法
実現主義とは、取引や事象が発生した時点でなく、経済的な効果が実現した時点で収益や費用を計上する会計原則です。この原則に基づき、特殊な販売契約(委託販売、試用販売、予約販売、割賦販売など)における売上収益の実現基準が定められています。
- 委託販売: 委託販売では、商品が実際に売れた日(または売上計算書が到着した日)を収益実現の日とします。決算処理時に売上が確定していれば、その売上を当期の収益として計上します。
- 試用販売: 試用販売では、顧客が商品を試用後に購入を決定することで収益が実現します。従って、試用期間中は売上を計上できません。
- 予約販売: 予約販売では、予約金を受け取ったものの、決算日までに商品やサービスが提供されていなければ、その分の収益を繰り延べる必要があります。提供が完了した部分のみを当期収益として計上します。
- 割賦販売: 商品を引き渡した時点で収益を実現しますが、割賦販売の特性(長期にわたる代金回収期間と回収リスク)を考慮して、貸倒引当金や代金回収費用の計上に特別な配慮が必要です。また、収益の実現を割賦金回収期限の到来や入金日にすることも認められています。
- 工事収益: 長期請負工事の収益計上は、工事進行基準か工事完成基準のいずれかを選択して適用できます。工事進行基準では、決算期末に進捗度を評価し、工事収益の一部を当期収益として計上します。工事完成基準では、工事完了時に収益を計上します。
- 製品等の製造原価: 製品やサービスの製造原価は、適切な原価計算基準に従って算定されなければなりません。
- 原価差額の処理: 原価差額を売上原価に配分した場合、損益計算書には原価差額を明示する必要があります。また、在庫資産に配分した場合は、貸借対照表の該当在庫資産に含めて表示します。
- たな卸資産の評価損: 在庫資産の評価損は、低価基準を適用した結果生じたもので、通常は売上原価内で表示しますが、特定の条件下では営業外費用や特別損失として表示することもも許されます。
- 内部利益とその除去: 企業内部での取引から生じる未実現の利益を内部利益と呼びます。内部利益の除去は、合併損益計算書で内部売上高を売上高から、内部仕入高(または内部売上原価)を仕入高(または売上原価)から控除し、さらに期末在庫から内部利益を控除することで行います。この控除は、合理的な基準に基づいて行うことが認められています。
- 特別損益項目: 特別損益には臨時損益(例:固定資産の売却損益、有価証券の売却損益、災害による損失)と前期損益修正(例:過年度の引当金調整、減価償却の修正、在庫資産評価の訂正)が含まれます。ただし、金額が僅少なものや経常的に発生するものは、経常損益に含めることができます。
- 法人税等の追徴税額: 法人税等の更正決定による追徴税額や還付税額は、税引前当期純利益に加減して表示します。ただし、重要性が低い場合は、当期の法人税負担として表示することも可能です。
- 将来の期間に影響する特定の費用: すでに支出が行われ、対応する役務が提供されたものの、効果が将来にわたって発生すると期待される費用は、その効果が及ぶ期間にわたって合理的に配分され、経過的に繰延資産として計上されます。
- 流動資産と固定資産の区別: 営業取引から生じる債権や債務は一般に流動資産または流動負債に分類されます。しかし、回収が一定期間内に見込めない債権や、一年を超える期間で費用化される前払費用などは、固定資産または投資その他の資産に分類されます。
- 貸倒引当金や減価償却累計額の表示: 貸倒引当金や減価償却累計額は、それぞれの資産が属する科目ごとに控除する形式で表示するのが原則ですが、一括して表示する方法や控除後の残額のみを記載する方法も認められています。