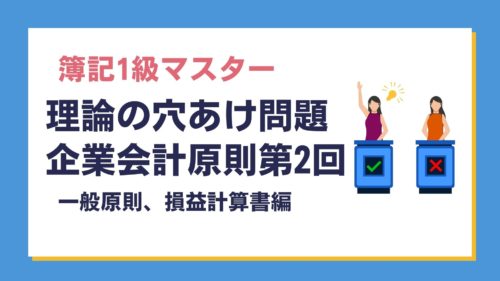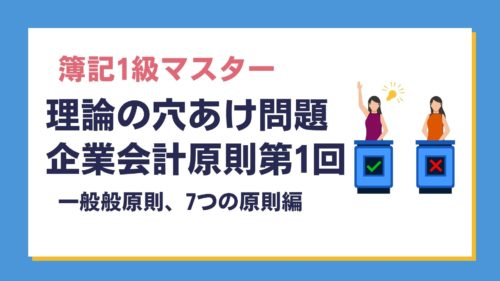(企業会計基準委員会 公表資料から一部引用)

目 的
1.本会計基準は、本会計基準の範囲に定める収益に関する会計処理及び開示について定めることを目的とする。なお、本会計基準の範囲に定める収益に関する会計処理及び開示については、「( )」に定めがあるが、本会計基準が( )して適用される。
答はこちら
企業会計原則、優先
会計基準
Ⅰ.範 囲
3.本会計基準は、次の(1)から(7)を除き、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示に適用される。
(1) 企業会計基準第10 号「金融商品に関する会計基準」(以下「金融商品会計基準」という。)の範囲に含まれる金融商品に係る取引
(2) 企業会計基準第13 号「リース取引に関する会計基準」(以下「リース会計基準」という。)の範囲に含まれるリース取引
(3) 保険法(平成20 年法律第56 号)における定義を満たす保険契約
(4) 顧客又は潜在的な顧客への販売を容易にするために行われる同業他社との商品又は製品の交換取引(例えば、2 つの企業の間で、異なる場所における顧客からの需要を適時に満たすために商品又は製品を交換する契約)
(5) 金融商品の組成又は取得に際して受け取る手数料
(6) 日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第15 号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」(以下「不動産流動化実務指針」という。)の対象となる不動産(不動産信託受益権を含む。)の譲渡
(7) 資金決済に関する法律(平成21 年法律第59 号。以下「資金決済法」という。)における定義を満たす暗号資産及び金融商品取引法(昭和23 年法律第25 号)における定義を満たす電子記録移転権利に関連する取引
4.顧客との契約の一部が前項(1)から(7)に該当する場合には、前項(1)から(7)に適用される方法で処理する額を除いた取引価格について、本会計基準を適用する。
Ⅱ.用語の定義
5.「( )」とは、法的な強制力のある権利及び義務を生じさせる複数の当事者間における取決めをいう。
答はこちら
契約
6.「顧客」とは、対価と交換に企業の通常の営業活動により生じたアウトプットである財又はサービスを得るために当該企業と契約した当事者をいう。
7.「( )」とは、顧客との契約において、次の(1)又は(2)のいずれかを顧客に移転する約束をいう。
(1) 別個の財又はサービス(あるいは別個の財又はサービスの束)
(2) 一連の別個の財又はサービス(特性が実質的に同じであり、顧客への移転のパターンが同じである複数の財又はサービス)
答はこちら
履行義務
8.「取引価格」とは、財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額(ただし、第三者のために回収する額を除く。)をいう。
9.「( )」とは、財又はサービスを独立して企業が顧客に販売する場合の価格をいう。
答はこちら
独立販売価格
10.「( )」とは、企業が顧客に移転した財又はサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利(ただし、顧客との契約から生じた債権を除く。)をいう。
答はこちら
契約資産
11.「契約負債」とは、財又はサービスを顧客に移転する企業の義務に対して、企業が顧客から対価を受け取ったもの又は対価を受け取る期限が到来しているものをいう。
12.「顧客との契約から生じた債権」とは、企業が顧客に移転した財又はサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利のうち無条件のもの(すなわち、対価に対する法的な請求権)をいう。
13.「工事契約」とは、仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約のうち、土木、建築、造船や一定の機械装置の製造等、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うものをいう。
14.「受注制作のソフトウェア」とは、契約の形式にかかわらず、特定のユーザー向けに制作され、提供されるソフトウェアをいう。
15.「( )」とは、履行義務を充足する際に発生する費用のうち、回収することが見込まれる費用の金額で収益を認識する方法をいう。
答はこちら
原価回収基準
この簿記1級の理論問題は、収益認識に関する会計基準についての理解を問うものです。主に、収益が認識されるべきタイミングと方法、およびそれに伴う会計処理と開示についての基準を設定しています。以下に、要点をまとめた解説を記載します。
目的
- 本会計基準は、収益に関する会計処理及び開示を規定することを目的としています。特定の収益については別途基準が設定されている可能性がありますが、本基準がその収益に対しても適用されます。
範囲
- 本基準は主に顧客との契約から生じる収益に適用されますが、以下の例外があります:
- 金融商品に関する取引
- リース取引
- 保険契約
- 商品や製品の交換取引
- 金融商品関連の手数料
- 不動産の流動化に関する取引
- 暗号資産や電子記録移転権利に関連する取引
- 契約の一部が上記例外に該当する場合、その部分は例外に沿って処理され、残りは本基準に従って処理されます。
用語の定義
- 「顧客」は、企業の営業活動から生じた財やサービスを得るために企業と契約した当事者を指します。
- 「取引価格」は、財やサービスの顧客への移転と引き換えに企業が得る見込みの対価の額を指します。
- 「契約負債」とは、財やサービスを顧客に移転する企業の義務に対して、企業が既に対価を受け取ったか、または受け取る期限が到来しているものを指します。
- 「顧客との契約から生じた債権」は、財やサービスの移転と引き換えに企業が得る無条件の対価に対する権利を指します。
会計処理の要点
- 収益の認識は、企業が顧客との契約に基づいて約束された財やサービスを移転した際に行われます。
- 収益の認識には、契約の同定、契約内の性能義務の同定、取引価格の決定、取引価格の性能義務への割り当て、そして性能義務の満たされた時点で収益を認識する、というステップが含まれます。
この基準により、収益の認識に関する一貫性と透明性が向上し、様々な種類の取引に対して明確なガイドラインが提供されます。